ARTIST

レイルロード・アース RAILROAD EARTH
オフィシャルHPバイオグラフィー
The Bandの最後のコンサートを収めたドキュメンタリー映画《The Last Waltz》に極上のシーンがある…監督のマーティン・スコセッシがドラマー/シンガー/マンドリン奏者であるリヴォン・ヘルムと音楽について語り合う場面だ。ヘルムの説とはこうだ。“まずリズムを固め、踊りたい気分にさせることが先決だね。すると、カントリー、ブルーグラス、ブルース、ショー音楽等、どんなジャンルを取り入れても最高のサウンドが生み出せる…”そこで詮索好きなインタビュアー、スコセッシはこう突っ込む。“それはなんていう音楽だい?”“ロックンロールさ!”明らかに別の回答を期待していたスコセッシは、肩透かしを食らって思わず笑い出す。“ロックンロールねぇ…”
意外に思われるかもしれないが、時にヘルムのこの主張がそっくりそのまま当てはまるケースがある。音楽を演奏する側のミュージシャンは、必ずしもそれがどこにカテゴライズされるのかということまで気にはしていない。ジャンルにこだわるのは、得てして音楽ライターやレコード会社の担当者といった肩書きの面々だ。
そう、レイルロード・アース(以下RRE)のメンバーもThe Bandと同様、自分たちの音楽がどうジャンル分けされるかということなどには一切気を留めない…ただプレイするのみである。彼らがバンド結成に至った2001年は、ちょうどアコースティック楽器によるユニットがブームを呼んでいた時期だった。RREのバイオリニスト/ヴォーカリストであるティム・カーボーンはこう回想する。“メンバー全員が、長い間いろいろなプロジェクトで演奏経験を積んできたミュージシャンばかりだからね。すでにあちらこちらのプロジェクトで共にプレイしたことのある顔見知りが集まったような形だ。ついにその時点で、全員が常に一緒にプレイすべきだと思い立ったんだよ。”
アコースティック・ギタリスト/リード・ヴォーカリストのトッド・シェイファーに続けてもらおう。 “だが当初は気楽にアイデアを持ち寄り、集まって何らかの音楽を演奏するというだけの集団だったよ。始まりはそのくらいルーズだったんだ。気が向いたときに集まり、好きな楽器を手に音を出して遊ぶといった程度さ。俺たちがようやくオリジナル曲や、このメンバーで取り上げたら面白いだろうと思えるカヴァー曲に取り組み始めたのは、そうやって半年くらい過ごしたあとのことだよ。”程なくして彼らは形を成しつつあった5曲のレパートリーを携えてスタジオ入りし、デモ音源を作り上げた。早速彼らのマネージャーが数箇所のフェスティバル主催者に出来上がったばかりのデモを送ったところ、思いもかけず…名門のテルライド・ブルーグラス・フェスティバルへのRREの出演がいとも簡単に決定した。彼らは即座にスタジオへ戻ると更に5曲をレコーディングした。それらの音源の集大成が、彼らのデビュー・アルバム、『ザ・ブラック・ベアー・セッションズ』である。
RREの旅はこうして始まった。以降、彼らはブルーグラスのレーベルとして名高いシュガー・ヒル・レコーズから『Bird In A House』(2002年作品)と『The Good Life』(2004年作品)という2曲のスタジオ録音アルバムを発売した。その間、コンサート会場での録音行為に何ら規制をかけないRREのポリシーに賛同するオーディエンスを含め、ツアー先からツアー先へとRREの後を追うファン・ベースは拡大し続けた。だがRREのメンバーは自分たちを特定の音楽シーンに押し込めようとする風潮に対しては不満を露わにする。それは決して他のアーティストに対する敵対心などからではない。既存のジャンル分けは彼らにとってあまり意味がない、というのが正直なところだ。カーボーンはこう指摘する。”“アコースティック楽器を使った俺たちの楽曲アレンジは確かに個有の優れた面を持っているが、かと言って俺たちは純然たるブルーグラス・バンドではない…だからこのカテゴリーだけに括られるのはおかしな話だ。一方、「ジャム・バンド」という呼び名はバンドよりもファンにとって都合のいい括り方なんだと思うよ。これは生粋のライヴ・ミュージック好きで、コンサートやフェスに集まってくるファンのためにあるカテゴリーなんじゃないかな。”
RREは明らかにステージングで魅せるバンドである…それは彼らの最新作に当たるライヴ・アルバム『エルコ』を聴けば、明白に伝わってくる…事実として彼らはジャムで本領を発揮する。インプロヴィゼーションによるソロ合戦がRREの大きな強みであることは疑う余地がない。だがRREというバンドが群を抜いた存在となった本当の理由は、彼らの作詞/作曲の能力の高さにある… 彼らが初回デモ録音でテルライド出演を射止めたのは、そこに収められた5曲のクオリティが驚くほど高かったからである。以降も彼らのソングライティングは日々向上に向かって突き進んできた。\\\r
フロントマンであるトッド・シェイファーの味のあるヴォーカルを原動力としたRREサウンドは、バンドのメンバー6人全員の卓越した音楽的才能と演奏技術を基盤とした流暢な楽曲アレンジで展開していく。マンドリン奏者ジョン・スキハンが指摘するとおり、“俺たちはその気になれば一日中だってインプロヴィゼ-ションを続けていられるんだよ。但し通常は単に曲の持ち味を生かすためだけにインプロヴァイズするまでだ。大半のレパートリーにおいても、ライヴで演奏する際にはなるべくスタジオ録音盤のアレンジを忠実に守るようにしている。しかし一部には生まれながらにしてインプロヴァイズするのに最適なスピリットを持った楽曲もあるからね。そういったナンバーではメンバーの誰もが暗黙のうちに飛躍を試みるんだよ。”シェイファーが続ける。“俺たちが最もこだわっているのは楽曲の質だからね。常にここに焦点を置いている。いい曲を起点とするからこそインプロヴィゼーションも映える。演奏におけるジャムの部分は、曲に対する「コメント」のようなものであり、曲に新たな色彩を加えるためのものでもある。曲自体がインプロヴィゼーションによるジャムに身を任せてくれている。そういった曲は俺たちのアプローチを好んで誘発してくるよ…そこで俺たちは様々な可能\性を探索しながら個々に音楽的アイデアを出し合い、その曲の新たな領域を切り開いてやるんだ…しかし、こういったジャムが単にもともとの曲の本質を浮き彫りにしているだけだと感じるケースもたまにあるよ”\\
白熱のインプロヴィゼーションを通じて曲に「コメントしよう」というRREメンバー全員の意識が一致すれば、彼らは本当に奔放なジャムで聴かせる… その力量については、ジャムというスタイルの先駆者であるグレートフル・デッドのベース・プレイヤー、フィル・レッシュも一目置いているほどだ。事実として、ミスター・レッシュがRREに自身のオープニング・アクトを依頼した際、メインアクトであるフィル&フレンズ・バンドの「フレンズ」とはRREのメンバーだった。その夜のコンサートを最高の形で終えるべく、自らRREのパートリーを数曲マスターして備えていたレッシュは、見事にグループに溶け込んで完全燃焼した。
つまり…RREはジャムにおいて誰にも引けを取らないが、それでも彼らは単なるジャム・バンドではない。彼らはブルーグラスに色濃く影響されているが、それでいて彼らは(ある意味ブルーグラス界でタブーとされている)ドラムスもアンプも使う。これはなんという音楽だろう? 以下はマンドリン・プレイヤー兼ヴォーカリストのジョン・スキ-ンによるこの難題への解釈だ。“俺はいつだってRREをストリング・バンドと呼ぶことにしてるよ。いわばアンプリファイドされたドラムス付きストリング・バンドだな。” ティム・カーボーンの見解はかなり面白い。“俺たちはカントリー&イースタンのバンドだよ!”トッド・シェイファーの意見はこうだ。“パワー全開のストリング・バンドってとこかな?はっきり言ってわからない。俺はこういう質問はあんまり得意じゃないからね。”さもなければ、アメリカの音楽文化をこよなく愛するかの偉大なドラマー/シンガー/マンドリン奏者のかつての言葉どおりだろう。“ロックンロール!
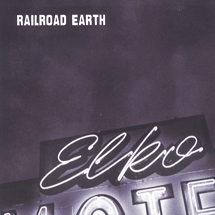
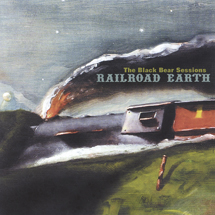
FUJI ROCKFESTIVAL 07 出演決定!http://www.fujirockfestival.com
http://www.myspace.com/railroadearth
トッド・シェイファー(Todd Sheaffer) - lead vocals, acoustic guitars
ティム・カーボーン(Tim Carbone) - violin, vocals
ジョン・スキーン(John Skehan) - mandolin, vocals
アンディー・ゴーズリング(Andy Goessling) - acoustic guitars, banjo, dobro, pennywhistle, saxophones and vocals
キャリー・ハーモン(Carey Harmon) - drums, hand percussion, vocals
ジョニー・グラブ(Johnny Grubb) - upright bass