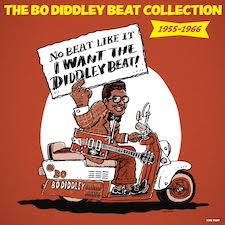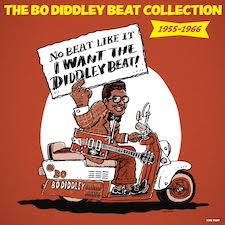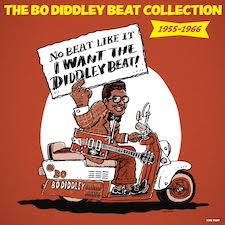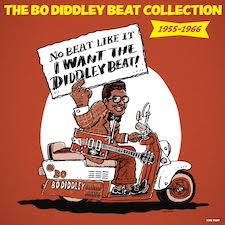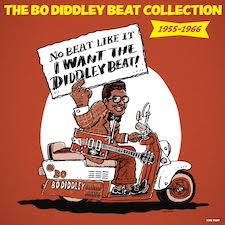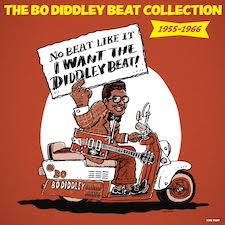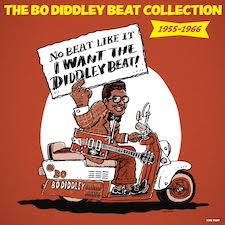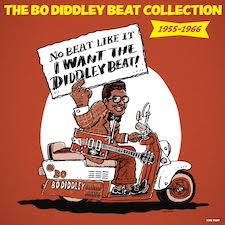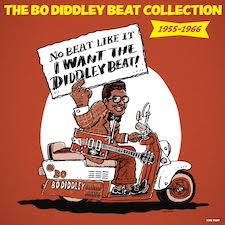V.A.『BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 : I Want The Diddley Beat !』
ODR7207 (JAN 4571534832079)
2024.12.27発売
M-1 BO DIDDLEY Bo Diddley 2’44’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Ellas McDaniel)
ボ・ディドリー・ビートの代名詞といえるこの曲「Bo Diddley / I’m A Man」で1955年にCHESS傘下のCheckerからデビュー。
元々はアフロキューバンのリズム、クラーベからきているリズムだが、アフリカ系アメリカ人の「ジュバダンス」や「ハムボーン」と呼ばれる足踏み、腕、脚、胸、頬などを叩いて踊る古くから伝わる遊び、ダンスのリズムがこのビートの起源と思われる。それを彼がロックンロール/ポピュラー・ミュージックの領域に到達させ、定着させたことがジ・オリジネーターと言われる所以だ。
他にもシカゴ・ブルースの裏番長ウィリー・ディクスンからの提供曲であり、ザ・プリティ・シングスのバンド名の由来にもなった「Pretty Thing」、「Bo Diddley」の続編といえる「Hey! Bo Diddley」、ストーンズがカバーした「Mona」など同様のビートを感じる傑作が次々と続く。
このデビュー曲がヒットしたことにより、黒人アーティストとして初のエド・サリヴァン・ショーへの出演という快挙を成し遂げるが、番組サイドから指示された曲(テネシー・アーニー・フォードの「16トン」)ではなく、生放送で本曲を演奏してエド・サリヴァンの怒りを買ってしまい以後出禁となってしまう。ボ・ディドリー本人の回想によるといろいろと誤解があったみたいだが、こういうエピソードも彼のキャラからしてなんだかロケンロール!と思えてしまう。
他にも、なぜ四角いギターなのか?の質問には「目立つから」とか、なぜマラカス奏者(ジェローム・グリーン)がいるのか?の質問には「ヤツはマラカスを振るくらいしか能が無いから」などロケンロールなセンス抜群の発言を多数もっている。まるでボ・ディドリーというキャラクターを演じて楽しんでいるかのようだ。何と言っても自分の名前(芸名)をデビュー曲のタイトルにしてしまうくらいなのだから。
M-2 MONA The Rolling Stones 3’33’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Ellas McDaniel)
1964年、Deccaからリリースの1stアルバムに収録。ストーンズによるボ・ディドリー・ビートは、このボ・ディドリーのカバーとザ・クリケッツの 「NOT FADE AWAY」をよりボ・ディドリー化させたカバーが知られている。僕もその例外ではないのだが、この両曲でボ・ディドリー・ビートの虜になった人も多いのでは?そして最初は「NOT FADE AWAY」もボの曲だと思っていた人も多いかと。
ボ・ディドリーがいなければアルバム「Between The Buttons」に収録のボ・ディドリー・ビートを用いたオリジナル曲「Please Go Home」も「Diddley Daddy」スタイルの低音ギターリフが印象的な「19th Nervous Breakdown」(19回目の神経衰弱)も、さらにはボの相棒ジェローム・グリーンのごとくマラカスを振るミックのイカしたパフォーマンスもなかったかもしれないのだ。
昔から好きだったのはもちろんのことだが、大貫さんの「Roots Of London Nite」シリーズや「Willie Dixon SONGBOOK 1947-1964」を制作したことや、来年の発売を予定して現在レコーディング中のサリー久保田プロデュースによる謎の女性アイドル・ユニットがこの曲をカバーしていることでボ・ディドリー・ビートの魅力を再確認できたのが本作を作る大きなきっかけとなった。
M-3 NOT FADE AWAY The Crikets 2’21’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Norman Petty/Charles Hardin=Buddy Holly)
1957年にBrunswickからザ・クリケッツ名義でリリース。作曲クレジットもチャールズ・ハーディン・ホリーのファースト・ネームとミドル・ネームからチャールズ・ハーディンとなっている。
「That’ll Be The Day」や「Peggy Sue」の共作者としても知られるクリケッツのドラマー、ジェリー・アリソンは段ボール箱を叩いてこのビートを生み出している。
M-4 YOU’VE DONE IT AGAIN Andy & The Live Wires 2’13’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Robert Anderson)
ネブラスカ州オマハ出身のアンディことロバート・アンダーソンは、ライブ・ワイヤーズを従えて1960年に地元のレーベルApplause Recordsから本曲をリリース。翌年にはLibertyからもリリースされている。
エルヴィスの「(Marie’s The Name) His Latest Flame」(マリーは恋人)やジーン・
ヴィンセントの「IN LOVE AGAIN」などと同様にロカビリー・スタイルにも浸透したボ・ディドリー・ビートを聴くことができる。
M-5 TURN ME LOOSE Sleepy LaBeff And His Versatiles 2’16’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Troy Caldwell)
スリーピー・ラベフ(Sleepy LaBeff)はスリーピー・ラビーフ(Sleepy La Beef)として知られるロカビリー、カントリー、ゴスペルなどルーツ・ミュージックを幅広く歌って親しまれたシンガー。本曲はスリーピー・ラベフ・アンド・ヒズ・ヴァーサタイルズ名義で1961年にマイナー・レーベルCrescentからリリースされている。
こちらもロカビリー・スタイルでエルヴィス風な歌もイカしている。
M-6 I WANT CANDY The Strangeloves 2’33’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Bob Feldman/Jerry Goldstein/Richard Gottehrer/Bert Berns)
「Roots Of London Nite Vol.1」にも収録されたロンナイクラシックスともいえるボ・ディドリー・ビートを使った人気曲。
プロデュースチームであるボブ・フェルドマン、ジェリー・ゴールドスタイン、リチャード・ゴッテラーによって作られた架空のバンド、ザ・ストレンジラヴスは、プロデューサー、バート・バーンズが中心となって設立したBang Recordsから1965年に本曲をリリース。彼らはこの曲以前にも1963年、ガール・グループ、エンジェルスの「My Boyfriend’s Back」などのヒット曲を手掛けている。このグループの「Jamaica Joe」(Roots Of London Nite Vol.3に収録)も彼らの作品だが、SKAのビートをいち早く取り入れるなどビートに対する敏感さがうかがえる。
M-7 WILLIE AND THE HAND JIVE Jo Ann Campbell 2’27’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Johnny Otis)
「Roots Of London Nite Vol.3」にも収録の本曲は1962年にABC-Paramountからリリースされたアルバム「For Twistin’ And Listenin’ / Boy Crazy」からの一曲。
アラン・フリード主演、1959年のロックンロール映画「Go, Johnny, Go!」でも知られるロカビリーの先駆者の一人といえるロッキンガール、ジョー・アン・キャンベル。実はこの映画のサントラに収められている彼女の曲はボ・ディドリーから提供された「Mama (Can I Go Out Tonite)」なのだ。そしてボ・ディドリー・ビートを使用していることで知られる本曲は「リズム・アンド・ブルースのゴッドファーザー」と呼ばれるジョニー・オーティスがオリジナル。後にエリック・クラプトンやジョージ・サラグッドがカバーしたことでも知られているが、本作に登場するクリケッツ、ストレンジラヴスもカバーしている。ジョニー・オーティスによるとこの曲はボ・ディドリー・ビートとは無関係らしいが「Bo Diddley」のヒットなくして「WILLIE AND THE HAND JIVE」のヒットはなかったのではないだろうか。
M-8 I WISH YOU WOULD Billy Boy 2’41’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Billy Boy Arnold)
「時代を超えたシカゴ・ブルースの名曲」とも言われる本曲は、ボ・ディドリーの影響下というよりもボ・ディドリー・サウンド・スタイルそのもの。というのもボが最初にCHESSに持ち込んだデモテープでもこのビリー・ボーイ・アーノルドがハーモニカを担当し、CHESSの初期の作品でも彼がハーモニカを担当している曲も多い。いわば同士なのだ。実際に本曲もボと共作してCHESSサイドもボの2枚目のシングルとして予定していたらしいが、彼は何を勘違いしたのかCHESSサイドが気に入っていないと思い込みライバルレーベルのVee-Jay Recordsにこの曲を売り込んで契約してしまう。 Vee-Jayサイドからは歌詞を変えるように言われ、歌詞を変更して出来たのが本曲というわけだ。ボ・ディドリー談によると「ヤツはCHESSから嫌われていた」というから、今となっては何が本当なのかわからないのもまたロケンロール!だ。
後にヤードバーズがカバーしていたりデヴィッド・ボウイの全曲カバーのアルバム「Pin Ups」でも取り上げられている。「Diddley Daddy」や「Bo Diddley Is A Lover」スタイルのギターリフを使って彼の代表曲になったということだけは間違いないだろう。
M-9 STORM WARNING Mac Rebennack 3’12’ BO DIDDLEY BEAT COLLECTION 1955 – 1966 ODR7207
(Mac Rebennack)
後にドクター・ジョンとしてニューオーリンズ音楽の伝道師としても名をはせるマック・レベナック。彼はまだ10代の中頃からレコーディング・スタジオに入り浸りレーベルのA&R、セッション・ミュージシャン、プロデュース、作曲など各方面で活躍。最初はギタリストとして活動していたが1961年頃、左手薬指に銃撃を受けるというアクシデントに見舞われた以降はキーボーディストへと転向。
本曲はそのギタリスト時代、1959年にRexからソロ名義でリリースされている。セッション・ギタリスト時代の代表曲ともいえるナンバーだが、荒くれたギター・サウンドがなんとも魅力的。それがまたボ・ディドリー・スタイルというのが興味深い。